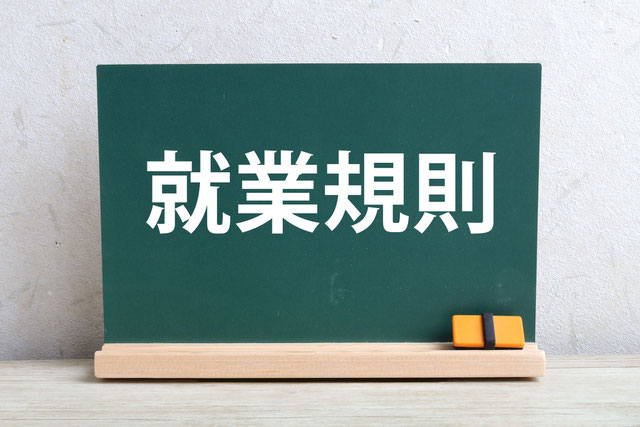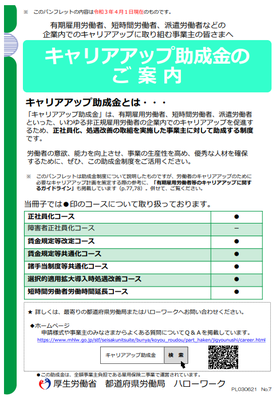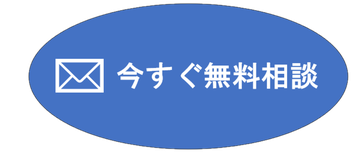就業規則とは?
1.就業規則の重要性
就業規則は、企業と従業員との間で労働条件や職場ルールを明確に定める基本文書です。
これを整備することで、トラブルや誤解を未然に防ぎ、健全な労使関係と組織運営が実現します。
2.労働条件の明確化
就業時間・休日・休暇・賃金・退職などの条件を文書化することで、従業員が安心して働ける職場になります。
3.法改正への対応
労働基準法や育児・介護休業法など、法律は年々改正されています。
就業規則も最新法令に即してアップデートすることが必要です。
4.企業のニーズに応じたカスタマイズ
フレックス制度やテレワーク、裁量労働など、現代の働き方に合った内容へ柔軟に対応可能です。
5.就業規則の基本定義と位置づけ
-
賃金・労働時間・休日などの労働条件
-
服務規律や社内ルールを統一的に定めた基本ルール
労働契約(個別)< 就業規則(全社共通の基本ルール)
6.就業規則作成が義務となる事業所
-
常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用している場合
-
法人単位ではなく、事業場単位で義務が判断されます
→ 労基署への届出が必要/未提出は罰則の対象
7.就業規則がないことで起きる問題
-
労使トラブル時に行政に指摘され、会社側が不利に
-
義務のある事業所で未作成・未届出だと法違反に
-
助成金申請にあたって就業規則の提出が必要になることも
8.就業規則で定める3つの記載事項
| 区分 | 内容例 |
| 絶対的必要記載事項 | 労働時間・賃金・退職・解雇など |
| 相対的必要記載事項 | 退職金制度、休職制度など(制度がある場合は記載義務) |
| 任意的記載事項 |
表彰・慶弔など自由に定めることができる事項 |
出典:厚生労働省「モデル就業規則」
9.残業時間の記載がないリスク
就業規則に残業の有無が明記されていないと、36協定を締結していても残業命令が無効になる可能性があります。
→ 安全のため「残業の有無」を就業規則にも記載しましょう。
10.就業規則で明文化すべき主要ルール
-
正社員・パートの定義
-
所定労働時間
-
賃金の支払方法・割増計算方法
-
定年制・退職事由など
【絶対的必要記載事項の具体例】
(1)割増賃金の計算方法
(2)特別休暇の取扱い(範囲・有給/無給など)
(3)解雇の事由(業種・実情に応じた具体化が必要)
11.テンプレート利用の落とし穴と対策
よくある誤り
-
テンプレートをそのまま流用
→ 会社に合わず、逆に不利な運用になることも
効果的な使い方
-
行政例・書籍・同業他社などから3種類以上収集
-
共通点や独自性を分析
-
自社に合ったルールを抽出し、必要部分を補完
12.定めておくと良い追加規定
正社員転換規定
→ キャリアアップ助成金(正社員化コース)で最大57万円支給
→ 条文の不備があると不支給になる恐れあり
休職規定
→ 曖昧だと復職困難な社員の長期在籍や保険料負担が発生
→ 明文化で対応ルールの明確化・リスク軽減
13.就業規則のアップデートは必須!
例:2019年施行「年5日の有休取得義務」
→ 古い就業規則では法令違反のリスクがあるため、定期的な見直しが重要です。
14.就業規則変更時の注意点
-
原則:労働者と会社の合意による労働条件の変更
-
例外:合理的な内容+従業員への周知で、就業規則による変更も可能
→ 初回作成時から、慎重な内容検討が求められます。
15.自作 vs 外注(専門家)
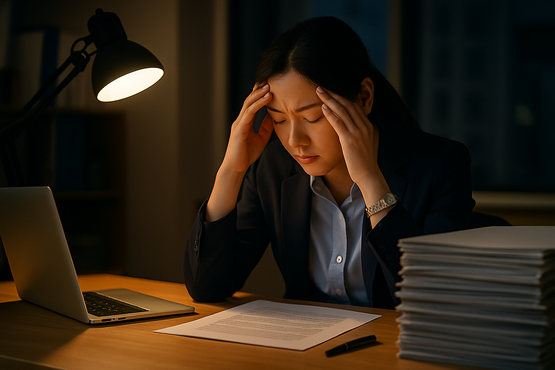
【自社で作成する場合】
メリット
-
社内実態を反映しやすい
-
規則全体の構造が理解できる
デメリット
-
時間と労力がかかる
-
法的なリスクの見落としが生じやすい

【専門家に外注する場合】
メリット
-
専門知識による的確な条文整備
-
作成の負担が少ない
デメリット
-
費用(10万~100万円)
-
要望の細部まで反映には工夫が必要
▶ 就業規則は、「会社を守り、働く人も守る」法律文書です。
法改正・トラブル対策・助成金対応など、今の時代に合わせた整備をおすすめします。